 |
3日目 |
知らない空。
知らない海。
唇を舐めれば、ここ暫く潜っていた海とは違う潮の味がした。
ただ延々と広がる海を前にエールステゥはため息をつく。
「参ったね」
それはどこまでも本音だ。まさかこんな事態になろうとは誰が予想できただろうか? 何らかのトラブルが起きる可能性こそ想定はしていたが、それが別世界への強制転送……等という無茶苦茶なものになるなんてさすがに思ってもいなかった。
謎の石製の『門』がある浅瀬の周辺を一通り探索してみたが状況は芳しくない。それまでは「もしかしたら別の世界というのは気のせいで、遥か遠方の土地に飛ばされたのでは?」と思っていたが調べていくに従ってその可能性が見事に潰されてしまったからだ。
エールステゥは手を眼前に翳した。意識を研ぎ澄ませる。
「蒼の輝き……揺蕩いし水面の精霊よ……」
それは慣れた手順の筈だった。水に属する精霊たちに呼びかける為の呪言。何時もならば、こうして囁いて喚んでやれば、直ぐに精霊たちからの反応が帰ってきたものだった。……が、現状は異なる。
「……、やっぱり反応はない……か」
探索中に精霊の力を借りようと思って気付いた、ここが別世界であるという可能性を裏付ける事実のひとつだ。
元々精霊というものは、土地や環境に深く根ざした存在である。こうして呼び掛けても反応がない、という事は彼らの影響が及ばない世界に自分が居るという証となるだろう。もしもコチラで精霊の様な何かの力を得たいのならば、そういった者達と改めて交渉をするなり契約しなければいけなさそうである。
ならば精霊の力を借りなければなんとかなるのか、という話だがそう事は簡単ではない。勿論、エールステゥはその方法も試みたのだ。が、結果は残念なものだった。術式を練ることが出来ても、それを発動させる事が出来なかったのだ。それも、何らかの妨害を受けて。
その妨害が何なのかまでは現時点では良くわからない。が、現状頼れるのは自分の身一つ、という事が嫌というほどに証明されてしまったわけである。
「だからこそ、現状打破の為にはちょっと本気で頑張らないと駄目っぽいよね」
やれやれ、と難しい顔で海を見ながらエールステゥはその場で準備運動を始めた。これからやろうとすることはなかなかにハードだ。事前にしっかり身体を準備しておかなければ、間違えれば生命にも関わる。その視線の先には遥かな大海原が広がっていた。島の影は不思議なほど少ない。……というか殆ど無い。
この世界は海だらけなのだろうかと呆れるような光景ではあるが、それでも救いはある。この浅瀬からかなり離れた海の上に、島のようなものがあったのだ。あそこまで辿り着けば、何らかの進展は得られるかもしれない。
問題なのは地続きではなく、更には周囲に船影らしきものすらなく、そしてこの浅瀬は砂浜しか無い……という所である。島まで行きたくとも手段が殆ど無いのだ。だからといってエールステゥはその程度であっさり諦めて泣き寝入りするようなか弱い女ではなかった。
道がなく船はない。
ならば答えは簡単だ、あの島まで泳げばいい。
幸い、長時間泳ぐことには昔とった杵柄ということで慣れている。精霊の加護なし、という現状は正直辛いところだがこのまま海のど真ん中で座り込んでいても進展はないのだ。防風林すらない島というにもお粗末な砂の浅瀬にずっといるのも正直危険でしか無い。何と言っても、温まるための火を維持する薪すら無いのだ。今はまだ良いが、そのうち濡れた身体のせいで体温を奪われ弱ってしまえば移動すらままならなくなる。
行動は早いほど良い。迷うぐらいならば先がわからないにせよ前に進んだほうがよっぽどマシだ。
「さぁて……久々の遠泳だからね。気をつけながら泳がなくっちゃ」
しっかり体が温まりほぐれたのを確認すれば、準備完了。
気合も充分に、エールステゥは勢い良く海へと飛び込んだ。
目指すは、唯一の島影。
その目標をしっかりと見据えながら。
※ ※ ※ ※ ※
…——そうして、浅瀬を出発してかなりの時間がたった頃。
「何というのか……渡りに船、って本当こういう事だよねぇ」
泳いで渡るつもりが一転、まさかの船上の人となっていたエールステゥは空を見上げて苦笑を浮かべた。乗っているのは二人か或いは三人ぐらいが限界だろうカヌーにも似た小舟である。後方では、練り櫂を握る中年の漁師の姿があった。たった一本の櫂を器用に操り進む先には、目指していた島の影がある。
何の事はない。泳ぎ始めて数時間した頃、近くを通りかかったこの漁師にエールステゥは拾われたのである。最初は水難事故の被害者かと思われていた様で、人の良い漁師の男は随分と慌てていたが、コチラがのんきに泳いでいる様子を間近で確認すると呆れたように天を仰いでいたのを思い出す。
結局はこうして舟に引き上げられ、島まで送ってもらっている訳だが……問題がないわけではなかった。
「まさか言葉が通じないとは、ね」
同じ世界ですら、国や土地が違えば使う言葉が違うなんてザラなのだ。世界が違えば更に混乱する羽目になるのは当然だと何で考えなかったのか。まあそれでもボディーランゲージは無事に通じたようで「向こうの島に渡りたい」と何度も指差して泳ぐように手を動かせば、納得した様子でこうして向かってくれているわけだが。
しかし言語が通じないのは正直大問題だ。今後の情報収集に大きな壁が出来たことになる。さてどうしたものか、とそんな新たな問題に頭を悩ませている内に舟は島へと到着した。
島の端にある港は、然程大きくもないがそれなりに栄えているようだった。木製の浮き桟橋には幾つもの漁船が括り付けられ波間に揺れている。桟橋の向こうにはテントのようなものが無数に広げられていて賑やかな声がしていた。漁師町にはよくある光景だ。もしかしたら、海鮮市場か何かが開かれているのかもしれない。
舟から桟橋へと上がればようやっと人心地がついた気がしてエールステゥは安堵の息をつく。だだっ広い海の上はやはり不安なものだ。こうして、地に足がつくだけで安心してしまえるのだから。今更ながら全身にじんわり広がる疲労感を感じながら、エールステゥは漁師へと視線を向ければ一礼した。
「ええと、とりあえず……ありがとうございました!」
「——! ——♪」
「……うぅん、やっぱり判らない」
ニュアンスや表情で機嫌が良さそうなのは判るのだが、コチラの礼の言葉も通じているかは怪しい。とはいえ、頭を丁寧に下げれば気にするなと慌てる素振りで漁師は首を横に振って見せているので誠意は通じたのだろう。そう思いながら立ち去ろうとしたのだが、
「——」
「……え?」
何故か手招かれた。そして続いて漁師は、桟橋に舟を固定すると自分を先導するように前へと出てそのまま市場の方へと歩いていってしまう。かと思えば、振り返ってまた手招く仕草。
「着いてこい、って事?」
現状、頼れるものは何もない。護身用の武器すら、あの時弾き飛ばされて手元にはないのだ。確かに恩人とは言え、見知らぬ人物に着いていくことに不安を感じていないといえば嘘になるだろう。が、エールステゥは覚悟を決めた。毒を食らわば皿まで、だ。
先をゆく漁師の背を追いながら周囲を見回す。無数の人々は人間も多いがソレ以外の種族の姿も多く見られた。獣のような耳をした者もいれば、鱗で覆われたトカゲのような外見の者もいる。全てが漁師というわけでなく、身に付けた品々から察する感じ同業者に近い者達も居る様子である。
ただの漁師町だと思っていたが、違うのだろうか? 首を傾げたその時だった。目の前で立ち止まっていた漁師が、まるで「此処だ」と言うようにある建物を指差す。そこにはこんな看板があった。
「海底探索協会……テリメイン支部?」
複数の文字で書かれた看板だ。殆どは読めないものだが、そのうちのひとつは何とか読めた。海底探索協会。初耳である。が、こうして読める文字があるということは筆談も可能なのだろうか。
とりあえず入ってみろ、と言わんばかりに指差す漁師に見送られながらエールステゥはその扉を潜ったのだった。
※ ※ ※ ※ ※
その後、話はトントン拍子に進む。
まず、海底探索協会に協力しこの世界の探索をする事を条件に預けられたスキルストーンのお陰で意思疎通が出来るようになった。更に、最低限の前金と失った得物の代わりに魔導石をもらったのである。後は最終試験で合格をもらうだけ、となったエールステゥは市場の片隅でさて、と思考を巡らせた。
遺跡探索は慣れたものだが、世界が異なる上に本来の力を一欠片すら使えない現状、一人では危険かもしれない。チラホラ聞く話によれば海賊も居るとか居ないとか。となれば味方が一人でも欲しかった。しかしどうやって集めたものか。
「島の鑑定師のところでバイトが出来てるのはイイ経験になってるけどね」
最終試験まで暫くあるという事で、この世界の知識を得る目的も兼ねてそんなバイトに勤しんでいるのである。お陰でスキルストーンが無くても最低限の共通語は使える様になったし、情勢も多少は分かる様になった。ちなみに、今はちょっと出かけている鑑定師の代理で店番の真っ最中だったりする。
とはいえ、このままバイト暮らしで終わる訳には行かないのだ。試験までには仲間を見つけたい。さてどうしよう。そんな思考に耽っていた矢先である。
「ねぇ、おねーさん。悪いんだけどさ、鑑定頼める?」
顔を上げる。声を掛けてきたのはまだ二十歳には届かないだろう幼さの残る少年だった。よく鍛えられているのだろう細身ながら絞り込まれた身体は年の割にがっしりしていて、だからか少し大人びても見える。その手には少し泥で汚れ海藻のこびりついたランプの様な物体があった。
「鑑定……このランプを?」
「そう。遺跡探索の練習で潜ってたら見つけたんだ。売れる代物なのかなって」
ちょっと待ってね、と前置いてランプを受け取る。とても軽い。表面の汚れを丁寧に清水で洗い清め、綺麗な皮の布で拭いてやればその鮮やかさは増した。海の底に在ったのだろう代物だが状態はかなりいい。……が、エールステゥは眉根を寄せる。
「これ、普通のランプじゃないね……呪物みたい。何か強い力が封じられてる」
「えっ!? じゃあ売るのは?」
「少なくとも普通の人は欲しがらないかもね」
呪物は余程安全性がわからないと欲しがる者は少ない。所持して呪われては困るからだ。かといって解呪するとなると逆にお金がかかる。売り払ってもマイナスになりかねない事を伝えながらランプを返せば、あからさまにがっかりとした表情を浮かべる少年。
その手がランプの表面を撫でる様に滑った、その時だった。
『…——我を呼び覚ましたのは汝か、人間』
黄金色に輝くランプから、煙のような物が吹き出した。それは筋骨隆々な人の腕にも似た形状を取り少年を指差している。性別の曖昧な厳かなその声はランプから響いている様だった。
『我は、呼び出した者の願いを叶える魔神である』
驚きのあまり声をなくす少年とエールステゥ。
そしてどこか威厳たっぷりに佇む魔神のランプ。
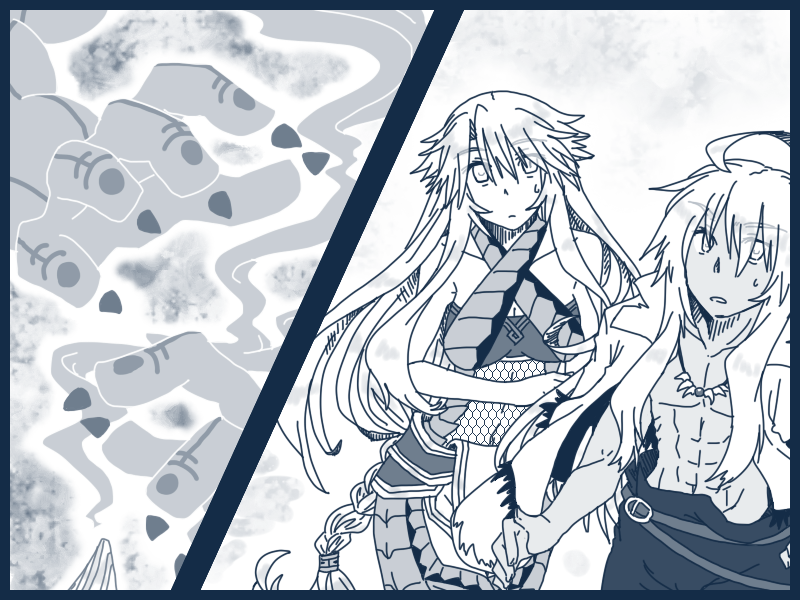
…——これが、エールステゥが共に旅をする仲間と出遭った初めての瞬間なのだった。