15日目
目を覚ます。
見上げた先には、木目やシミの形まで覚えてしまう程度には見慣れた宿の天井があった。身動ぎすればギシリとベッドが微かに軋む音がする。顔を埋めた掛け布団からは、ほんのりとお日様の匂いがした。
寝転がったまま首を軽く傾ける。ベッドの右横の壁にはそう大きくもない両開きの窓が一つあった。カーテン越しに差し込む光はまだ淡い。肌に感じる空気の気配からしても、まだ明け方なのだろうか。
屋根の上に止まっているのか、或いは近くを飛んでいるのだろう鳥の囀りを聞きつつ、身を起こす。ぐしゃぐしゃになっていた髪の毛を手櫛で軽く整えながら、空いた側の手でカーテンを軽く避ければ覗くのは雲一つない青空だ。とはいえまだ色は薄い。日の出からさして時間がたっていないのだろうと推測しながら欠伸を噛み殺す。
ベッド脇の床頭台に手を伸ばした。上に置いていたはずの代物を手探りで引っ掴み引き寄せる。ジャラリと鎖の音が鳴って、掌に収まったのは小さな銀の懐中時計だった。とある冒険の最中に手に入れたソレは冒険者としてそれなりの年数は愛用している品だ。
常に街中にいるならばともかく、依頼で遠方に赴けば時報を告げる鐘すら無い小さな村が拠点になったり、或いはそんなものすらない大自然の中に身を置く方が多い。時刻を正確にしる必要はさしてないにしても、現実的にどれだけの時間が経過したかというのは依頼に対するひとつの目安にもなる。そういう時、ねじ巻き式のこの懐中時計は大層便利なのだった。
手にとった懐中時計は蓋付きのしっかりした代物である。竜頭を押せばその蓋はパカリと開いて、とてもシンプルな盤面が覗いた。針が指し示す時刻はまだ六時を回ってすらいない。随分と早起きしてしまったものだ、と目をこする。
もう一度寝ても良いかもしれない。さすがにこんなに早い時間に起き出した所で冒険者たちは誰一人起きていないだろうし、まず朝食すら出来ていない事だろう。今頃、階下のカウンター向こうは厨房で宿の親父さんが皆の朝食を作っている頃合いだろうから。
再び床頭台に懐中時計を戻して、ベッドに潜り込む。まだ人肌のぬくもりをじわりと残していた寝台は、横になれば意識を眠気に誘った。とろり、と瞼が落ちていく。
目を閉じれば闇が広がり、波の音がした。
ちゃぷり、ちゃぷ、ちゃぷ。
その音は子守唄には最適にも思えたし、……まるで自分を嘲笑う笑い声のようにも聞こえた気がしたけれど。
眠りに落ちた意識にはもはや、判別しようがないのだった。
※ ※ ※ ※ ※
そして意識は覚醒する。
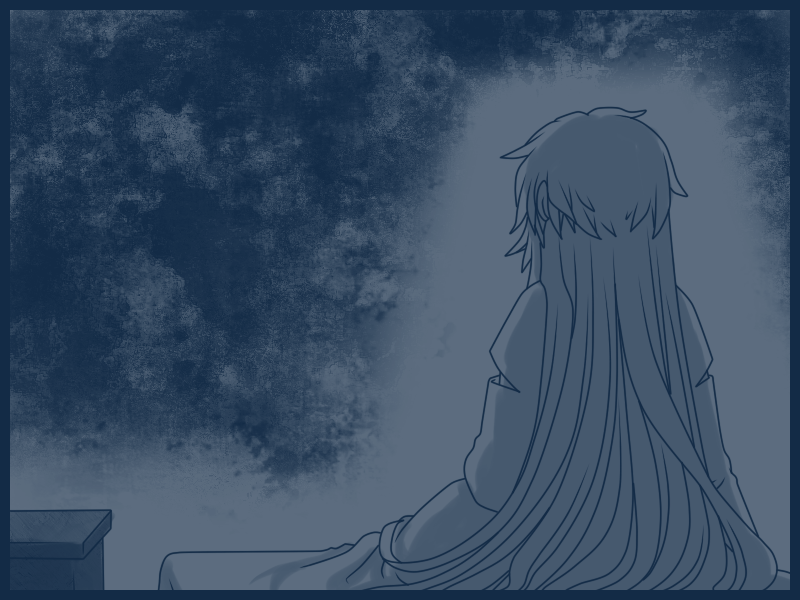
ガバ、と音を立てる勢いで身を起こしたエールステゥは一瞬だけ混乱した。
目覚め、そして視界に入り込む景色が記憶にある懐かしい宿の物とは全く異なっていたからだ。
今、エールステゥが眠っていたのはとある海上拠点の一角にある宿の個室である。探索に出ている間はオルキヌスの漁船にある客室部分で睡眠することも多いが、常にソレではろくに身体を休められない。だから、たまにこうして適当な拠点に立ち寄りしっかりと睡眠を取り補給を行うのが常だった。
「……昨日の夜から、そういえば拠点に停泊してたんだっけ……」
オルキヌスの目の事もあるし、一旦しっかりと休憩を取るべきと判断したのだ。元々、消耗品が大分減っていた事もありその補給も兼ねての停泊だった事を思い出す。随分と寝惚けていたものだと自分で自分の思考に苦笑するしか無くてエールステゥは小さくため息を付いた。
ぼんやりと思い出す。夢を見ていた。確かにエールステゥは、夢を見ていたのだ。定宿としていた〝黄昏の梟亭〟、その自室で目覚める……という懐かしくも虚しい夢を。
「笑っちゃう……今更ホームシックにでもなってるっていうの? 私は」
あはは、と笑おうとして声は掠れた。言葉で軽く言うほど、笑い飛ばせるほどに強くない事をエールステゥは自覚しているからだ。
何となく理由はわかる。このテリメインという滅んだ海の世界にも慣れてきた事や、探索者としての生活にも多少こなれてきて余裕が出始めてきたからだろう。今までは前にがむしゃらに進むことだけを考えていれば良かったし、実際ソレ以外の余裕なんて欠片もなかったというのに、今の生活に慣れてきたせいでほんの少しだけ元の世界を懐かしむ余裕が出来てしまった。帰りたい、或いは懐かしい。そういう望郷の想いが、あんな夢を見せたのだ。
「生まれ育った土地を離れて冒険者になった頃でさえ、故郷の夢なんて見たこと無かったのに……」
こうして事故的に異なる世界に跳ばされるという災難を経て、それまで暮らしていた環境から放り出されただけでこうも弱くなるのか。ソレほどまでに、あの宿暮らしに愛着を感じていたという事なのかもしれない。
「ちゃんとあの部屋……残ってるかなぁ……」
あのお気に入りの懐中時計は、部屋に置き忘れてきてしまっていた。アンブロシアは時告げの鐘があったし、どうせまた宿に戻るのだからまあ良いか……と気にもしていなかったが今になればとても心配だ。
冒険者なんて家業は、明日をも知れぬものでもある。昨日旅立った冒険者が次の日には帰らぬ人になる……なんて事は日常茶飯事。他のチームがそうなってしまった知らせを宿で受け取る場に居合わせた事だってある。だから自分だけは大丈夫だ、などと思ったことはない。それでも、生きていると思われてる限りは帰るべき場所として宿の部屋は確保されている筈なのだ。
だけどもしこうして異世界に跳ばされたなんて思いもせず、どこかで野垂れ死んだと思われたら? そしてそういう知らせが宿に届けられたらどうなるのだろうか。居場所は片付けられ、遺品は処分され、そして……同じ部屋はまた別の誰かのモノになるのだろう。
ソレを思うと少し怖いのは、確かだった。
「……大丈夫。必ず帰るよ」
胸の奥で重くのしかかる不安を跳ね除ける為に敢えて声に出して呟く。
大丈夫だ。今までだって、困難はたくさんあった。でもどんな問題も蹴散らしてきたではないか。今回は難題が多いだけであって、別にまだ帰れないと決まったわけでもない。探索を進めて行けばきっと、解決法は見付かる筈なのだ。……だからまだ、落ち込むのも諦めるのも早すぎる。
「不安になってる暇なんて、無いんだから!」
うん、と頷けば再びベッドに潜り込む。
まだ周囲は静かで動き出す人の気配は殆どない。時計こそ無いがそれでも起きるには早い時間だというのは察して余りある。ならばやることはただ一つ。二度寝以外にありはしない。
再びまどろみながらもエールステゥは想う。
今頃、向こうで待たせている仲間は何をしているのだろうか……そんな事を。