 |
8日目 |
ヴィーズィーと名乗った仮面の人物が指定したのは、海底探索協会のある人工島から少し離れた船の墓場だった。どうやらこの付近は水深が浅くなっている上にあちこちに岩礁が存在するらしく、その影響もあってか潮の流れはかなり複雑化しているのが見て取れる。
「小さい小舟だと気をつけないと変なところに迷い込みそうで怖いなぁ……」
思わずエールステゥはぼやいた。
今回、この海域に訪れるにあたって市場で顔見知りとなった漁師達に交渉し、小舟を一隻借り受けたのである。さすがに安全とは言い難い場所だと事前にわかっている以上、関係のない誰かを巻き込むことは避けたかったが為だ。漁師達も、エールステゥが向かおうとする海域については多少は知っているらしく、大層心配されたことを思い出す。
大丈夫だ、と告げてここまで来た以上、無事に帰らなければ。
勿論、ヴィーズィーからの依頼も完遂しスキルストーンを手に入れなければ、海底探索協会の実技試験にも差し障る。
「さて、と。とりあえず様子を窺ってみないとだね」
気を取り直してエールステゥは小舟の上から周囲を見回した。
事前に話には聞いていたがなかなかの光景である。
そこは海の底に海底遺跡の存在する海域だった。その全貌は海の底にあるために海上からは見えないが、遺跡の姿は水面からでも微かに窺える。地盤沈下によるものか、それとも他の要因に寄るものかは不明だが、その殆どは崩れ瓦礫と化してしまっている様だ。その遺跡と岩礁が潮の流れを変えた結果なのか、海域には幾つもの船の残骸が見受けられる。風化しかけた古そうな物もあればまだそれほど年月の経っていなさそうな船もある様子からすると、かなり長い時間をかけて船の墓場と化していったのだろうか。
そういった朽ちた物ばかりだからか、見ているだけで物寂しくなる……そんな場所だ。廃船に棲んでいるのだろう海鳥の声と潮騒の音が微かにするだけで、生き物の気配は表面上は殆どしない。
が、こういう漂着物のある場所というのはつまりは遮蔽物が多いという事でもある。海というだだっ広く何もない空間よりも外敵に見つかりにくく安全で、同時に獲物に存在を悟られ難いという絶好のポイントだ。その陰に気配を殺して身を潜める存在があったところで何もおかしくはない。
エールステゥは、難破船の残骸の一つに小舟を慎重に近づけた。充分に距離が詰まったところでロープを投げ、難破船へと飛び乗れば小舟をそこに固定する。潮の流れで廃船にぶつかったり岩礁に乗り上げても困るし、それだけならまだしもうっかりこの海域から余所に流れていってもらっても困る。何といっても借り物だ。丁重に扱わなければ。
小舟を固定し終えればエールステゥは身支度を整える。相手は水中を自在に泳ぐ存在だ。こちらが不利な状態であることは既に確定している。なるべく万全の状態で挑まなければまず勝ち目はない。
「これでよし。後は体力と運と……私の腕次第」
元の世界の時の様に精霊の加護は得られない。生身と生身での戦いを思えば瞳を伏せ、エールステゥは自分自身に言い聞かせた。大丈夫だ、冒険者になってからは確かにそういう補助を得ていたとはいえ、それまでも十二分に自分は海で戦えていたのだから。その感覚を思い出せばいいだけのこと。
「……、…………、………………」
海を見つめる。
覚悟は決めた。後は立ち止まらない事だけを意識すればいい。
エールステゥは息を大きく深く吸えば海へと静かに飛び込んだ。
バシャン、と決して大きくはない水音が一つ響き……その姿は、波の底へと消え失せた。
※ ※ ※ ※ ※
潮の流れは想像していたよりも激しくはなかった。どちらかと言えばどうも水面近くの方が流れが速いらしい。逆に水底に近付くに従って水の流れの影響は少なくなってきたことにエールステゥはホッとしつつ泳ぎを進める。水温も悪くはない。遺跡や岩礁のせいで海水がせきとめられているからか、潜ればほんのり暖かかった。
(水深が浅いせいだねこれは……良かった。あまり冷えると体の動きが悪くなるから)
戦場は海中というアウェイ状態だが、これは正直ありがたい。そんな事を思いつつエールステゥは目を凝らす。水中の透明度はかなり高い。潜るほどに流れが途絶えるから砂がまき散らされる事も無いからだろう。どこから流れ込んできているのか不明な滞積した砂は白く鮮やかだった。難破船のあちこちには海草や貝類らしきものの姿がある。岩礁には珊瑚などの姿も見受けられた。
……が、不思議と魚の姿は少ない。海中はまるで、何かを恐れるかの様に静まりかえっていた。
(普通これだけ隠れる場所があって程良く暖かいなら、小魚ぐらい居るものだけど……)
怪訝に思いながらも崩壊した遺跡群の方へと泳ぎ出す。遺跡はその殆どが瓦礫と化して、かつての名残りすら窺うことが難しい程に傷んでいる。海流によって船がぶつかったりしたせいだろうか。それとも海に沈んだ時に崩壊してしまったのか。どちらもあるのかもしれない。何にせよ、傷跡と劣化の激しい遺跡を視線だけで素早くチェックする。
詳しく聞いた話では、この崩壊した遺跡の下敷きになるように海底洞窟はあるらしい。入り口は大きいが崩れた瓦礫や点在する難破船の陰になっていて分かり難い状態なのだとか。それを幸いに、ヴィーズィーの友とやらは海賊の手をかいくぐり此処に逃げ込んで難を逃れた……という話だ。
確かにこれほどややこしい場所だと海賊も入り込みにくいのは当然だろうと思う。潮の流れを読み間違えればうっかり座礁しかねない。そんな危険を冒してまで追うのは割に合わなかったのだろう。海賊という種の人達は、余程の理由がない限り獲物に相対する時に損得を第一に考えるものだ。必要以上に余計なリスクでは儲けにならないならば、あっさり撤退する事だって普通にする。特に海を生活の場とする彼らにとって船の無事は最優先である筈だ。理由は簡単、船がなければ海賊行為すら難しくなるからである。
ただでさえ厄介そうな相手がいるのだ。背後から刺される可能性が無いだけでも一安心と言えよう。気を取り直せば、エールステゥは話にあった海底洞窟の入り口を探るために泳ぎだそうとした。
その時だった。
(今……気のせいか、水の流れが)
変わったような。
そんな言葉を思い浮かべるより早く。本能的に感じたヒヤリとした予感に、思わず水を蹴る。体を捻る様に、回転しながらの回避行動をとって一秒も経たず、先ほどまでエールステゥがいた空間を高速で通過した者がいた。
(今のは……!)
体勢を整えながら視線を向けた先、そこには巨大な一頭のサメの姿がある。全長3メートル程、或いはそれ以上あろうか。その全身には歴戦の証か、大小さまざまな傷が刻まれている。特に目立つのは切り裂かれたような尾鰭の切れ込みと左の目を切り裂くように走る大きな傷だ。どれも痛々しげな傷跡だが、古いものらしく完全に塞がっている様子が窺える。
基本的に空腹でもない限り他の生物を進んで襲ったりはしない筈だというのに、このサメはひどく興奮しているようだった。あからさまな敵意がそのひとつしかない瞳からは感じられる。敵、或いは獲物を前に獰猛な魔物が牙を剥いている……そんな気配だ。
左の手に装備した魔導石に意識を向けながらも、ふと、エールステゥは思い出す。そういえばヴィーズィーは言っていた。友は海賊に深手を負わされた上で海底洞窟に逃げ込んだのだ、と。この海域はもしかしたらあのサメの縄張りなのかもしれないし、或いはその友が流した血が海水に紛れ込んでいるのかもしれない。だとすれば、この敵意の塊といった現状も仕方がない事だろう。
(何にせよ、その友達とやらを探すにはこの子をどうにかしないとダメみたいだね……)
運が良ければ遭遇する前に合流して脱出も可能かと思っていたのだが。さすがにそうも上手くは行かないらしい。
物理的に止める手段は今、自分にはない。使い慣れた剣は、テリメインに転移する事故が起きる直前、紛失してしまった。となれば、使えるのはこの手にある魔導石のみだ。幸いなのは、水中で扱う関係上か声による術式詠唱でなくとも魔術を行使する触媒と出来る性質だろう。ただし、それには時間がどうしてもかかる。少しでも時間を稼がなければ。
再び突進してきたサメをギリギリで回避する。それでも尾鰭の一振りを完全には避けきれない。重い一撃に突き飛ばされれば、思わず息を吐き出した。集中が途切れかけるが気合で繋ぎつつも慌てて歯を食い縛るエールステゥを余所に、サメの方は素早く身を翻す。さすがは海の狩人。獲物を前にすれば容赦はないという事か。舌打ちしたい気持ちを抑えて意識を研ぎ澄ませる。
これから扱おうとしている術は酷く繊細かつ複雑で難しい物だ。触媒を得て扱えることは事前に確認しているが、だからといって気楽に使えるものでもない。早すぎても遅すぎても駄目なその術式を丁寧に編み上げつつ、タイミングを図る。
再び体勢を整えたサメは、物凄い勢いで迫ってきた。突進の速度は先程以上だろう。回避しようとしたとして、今度はさすがに逃げる余裕はない。みるみる眼前に迫る巨躯を正面から睨めば、エールステゥは左手を敵へとかざす。
今がその時だ、とばかりに。
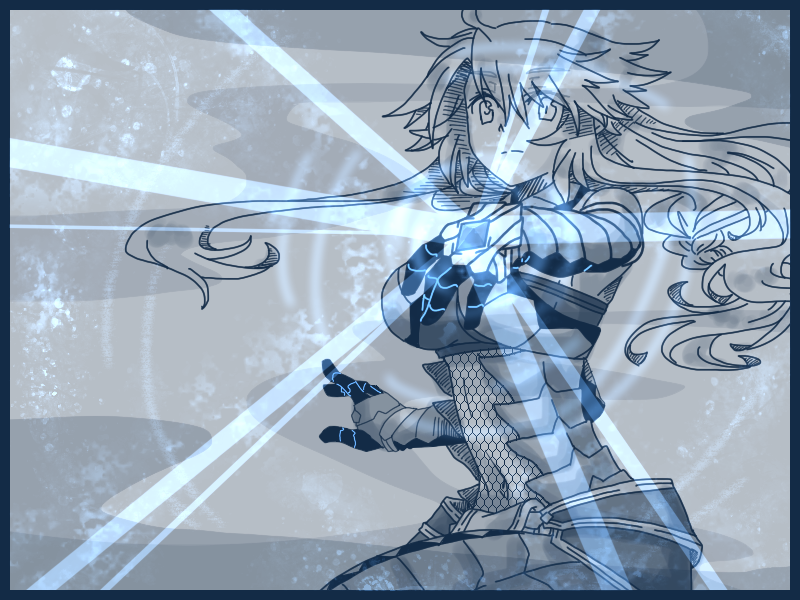
……次の瞬間。
蒼の輝きが煌めいた。
魔導石から光の波紋が放たれる。それに触れた瞬間、サメはそれまでの勢いを完全に無視してピタリとその場に硬直する。まるでその光景は、サメの時間だけが止まってしまったかの様な、あまりに不自然な硬直の仕方だった。腕を伸ばせばすぐにでも触れることが出来る距離で動きを止めたサメの姿に、エールステゥはニンマリと笑った。
狙い通りだ。今発動したのは『時間蝕』という対象の時間を止める魔術だ。以前に訪れたとある中継都市は賢者の塔と言う術師達のギルドのような場所で学んだもののひとつである。使い所が難しくなかなか実戦で使用する機会は今まで無かったのだが……今回は役に立ってくれた事にホッとする。人生、何が功を成すか分からないものだ。
ならば、と次の術式をエールステゥは編み始めた。これは一時的な処置にすぎない。時間止めは短時間しか不可能なのである。今のうちに次の手を打たなければいけないからだ。
もっとも、今回はサメの妨害もない。そう時間もかけず手早く編み上げたのは魔力で形成された糸で対象を拘束する『蜘蛛の糸』という術式だった。その糸は展開された途端にサメに巻き付き行動を阻む。これならば、ノロノロ泳ぐことは出来ても先程の様な暴力的な突進は不可能だろう。
(別に生命まで奪いたい訳じゃないしね)
元より、今回の目的は討伐ではない。こちらがヴィーズィーの言っていた友と合流しこの海域から離脱するまで大人しくしていてもらえれば充分なのである。サメのとりあえずの無力化を確認すれば、エールステゥはその場を後にした。
※ ※ ※ ※ ※
時折呼吸のために海上と海中を行き来しつつ、探すこと程なくして海底洞窟は見つかった。ちょうどサメと小競り合いが在った場所から近かったのである。相変わらず生物の気配はほとんど無く、まさかまた別に厄介な生き物がいるのではなかろうか、と不安に思いつつもエールステゥは腰の袋からひとつの道具を取り出した。海中でも扱える特殊なカンテラである。冒険者として普段も使っている代物で、持ち手の魔力を灯りに変換してくれるという魔法具の様なものだ。
洞窟の中は薄暗くわかりにくい。目立つ、という問題はあるがそれでも何も見えないほうが危険度は高い。灯りを灯せばエールステゥは不安を押し殺しつつ、洞窟の入り口脇にもしもの時の命綱用のロープを固定すれば、洞窟内へと泳ぎ入る。
洞窟はアチコチが崩落しあまり状態は宜しくないようだった。瓦礫も多く、行けそうで行けない道の方が多いかもしれない。灯りがあって良かった、と思いつつも奥へ奥へと進んで行く。暫く進めばエールステゥは海底から続く岩場がなだらかな坂のように上へと続いている場所に突き当たった。左右には洞窟の内壁だろう岩壁があるばかりで周囲を見回しても他に続きそうな穴や道は無さそうである。
(うーん……分岐はなし。後はこの坂を登ってみるぐらいしか出来そうにないね)
見上げれば、坂の上方は途中で途切れてしまっていた。どうやら水から上に出ているらしく、その先は窺い知れない。もしかして海底洞窟内に空気溜まりでもあるのだろうか。怪訝に思いながらエールステゥは上へと向かって泳げばそのまま水面に顔を出す。
そして、目を見開いた。
「……………………は?」
海面から見上げた、その眼前。
坂の上にとぐろを巻いて自分を見下ろしてくる蒼の竜が、其処には鎮座していたのだった。