12日目
精霊術。
どういったものか、と言われると一概にこうと言えない……そんな独特の術式体系をもつ技能のひとつだ。
精霊と友誼を結ぶことで力を得て奮う者。
精霊を屈服せしめる事で力を奪い奮う者。
精霊との契約を経て力を与えられ奮う者。
カタチとしては様々なものがあれど、結局のところ扱う力は同じものだ。
精霊の統べる力の顕現。
精霊術とはつまり、様々な根源の力を代行して奮うこと……とも言えるのだろう。
□ ■ □ ■ □
波の音がして、潮風が頬を撫でる。海の天気は山ほどではないがそれでも変化が激しい。だが、現状はその先行きを気にする必要は無さそうだ。今日もテリメインの海は快晴だった。雲一つない、というのも大袈裟だが実際にそれは間違いとも言えなかった。青い空は高く遠くまで澄んでいる。
「良い船出日和だねぇ」
「でももうちょっと風は欲しかったかなー……とは思うけどね。そしたら帆を張れたんだけど」
後ろで櫂を操るオルキヌスは、ゆったりと揺れる船の動きに身を任せるエールステゥへと苦笑交じりに返した。実際、風は穏やかで緩やかなものだった。気持ちは良いが……今ひとつ頼りない。船を押し出すほどの力はそこには無さそうだった。
とは言え船の動きは淀みがない。まるで水面を滑るように疾走る。それもこれも、スキルストーンの加護のおかげ……というのはきっと考え過ぎではないだろう。
「あとエルゥさん、魔神さん。そろそろ《アッシュフォードの門》が近いから準備を頼むよ」
「了解だよー」
『《門》か……汝、上手くやれよ』
「せ、責任重大だなぁ……本当」
含みを持ったランプがカタカタと笑うように蓋を揺らしつつ告げる言葉にエールステゥは肩を落とす。
実際、責任重大というのはモノの例えというわけでもないのがつらい所ではある。
「あのイフリートと契約、だっけ?」
「そうそう。私の扱う精霊術はそういう方式だから……多分、違う世界でも不可能じゃない筈なんだよね。土地の精霊の助力さえもらえるなら、この世界でも精霊術は扱える筈……というか。実践してみないと何とも言えないけど」
「そのセーレージュツ、だっけ? それってどういうものなのさ。俺、そういうマジュツ? とかってのが良くわかんないからさ」
「嗚呼、オルキ君の暮らしていた場所だと、魔術とかそういうモノ自体が珍しいってことなのかな」
「まあ……多分。あまり聞いた覚えはないかな」
『縁がなければ確かに耳慣れぬ言葉なのも仕方ない話であろうな』
成程。どれだけランプの魔神とエールステゥが魔術談義をしていた所で理解できないのも当然だろう。最近のつまらなさそうな顔はそれが理由か、と得心するエールステゥとランプの魔神である。しかし、魔術の概念が薄い相手にどう説明したものか、とエールステゥは頭を悩ませた。
「えっと……オルキ君は漁師歴、長いんだよね?」
「それなりにはってとこだね」
「それじゃあこういう事ってあった? 例えば船で遠方の漁場に出向きたい時に全然風がなくて困った……とか」
「確かにそういう時もあったりはしたけど……」
ソレが一体何なのか、と訝しげな表情のオルキヌスの反応を伺いながらもエールステゥは続ける。
「そういう時、風が吹くと嬉しいよね?」
「そりゃ当然嬉しいさ。でも、そんなの自然現象だし、俺には待つしか出来ないよ。スキルストーンみたいな便利なものがあるわけでもないしさ」
「だよね。普通、風が吹くのは自然現象。……でもね、例えば風の精霊がいたとしてその力を借りれたとしたら? どんな環境だって、望む風が得られる可能性がとても高いよね」
「……、……つまりそのセーレージュツってのはその風の精霊ってのに協力してもらう為の技術って事?」
「だいたい間違ってないね、その認識で」
「…………そんなホイホイ居るものなの?」
そういう存在は見たことがない、と言わんばかりの表情で周囲を見回すオルキヌス。実際に精霊とやらが居るなら視界の何処かに入らないわけがない、と首を捻っているのはやはり精霊という存在に対して半信半疑だからか。
『精霊はそう簡単に人前に姿は見せぬ。理由があるならば別として』
「それに居たり居なかったり、はあるかもしれない。環境とかにもよるし」
「環境?」
「水気の多い所に火の精霊は好んで近寄らない、とかそういう風に相性があるからだよ」
「……この間のイフリート、海の中に居なかった?」
『アレは例外中の例外だと思うがな』
流石にアレには呆れた、と言わんばかりのランプの魔神の呟きにエールステゥも苦笑を漏らす。
「本当アレはびっくりしたね。……まあさっきも言ったけど相性的に不利な場所に普通居ないのが当然なんだけど、それを覆せる場合も無いわけじゃないんだ」
「例えば?」
『弱点なぞ気にならぬ程度に強い力を持つ者……という事だな』
「そうそう。強ければ有利不利なんて関係ないしね。だから退屈だ、なんて余裕綽々な事を言ってたんだろうし」
「えぇ……でも倒せたじゃん、俺達。そんな強いのに人間程度に負けていいのかな?」
「あはは……精霊の強さが純粋に力の強さなのか、って言われると私達にも疑問に思う部分があるから何とも言えないのが現状かな。色々あるんだよ、きっと」
先日、エールステゥ達の進行を邪魔した炎の巨霊を思い出す。海中でも変わりなく燃え盛っていた姿を思えば、彼らにとって海は対して問題がない場所という事なのだろう。もっとも、あの精霊が本気を出していたのかは正直怪しいとも思うわけだが。彼はエールステゥ達をただ試していたというだけの気もするのだ。
「何にせよ、精霊は色んな所に居るんだ。それこそ、目に見えないようなカタチでね」
『名と確たる自我を持った個体の姿で顕現する者の方が珍しい話ではある』
「そうそう。逆に言えば、周囲に満ちている力の結晶体が精霊……とも言えるのかな」
「この空気みたいにアチコチにその精霊とやらの影響があるってこと?」
「その通り。そしてあのイフリートみたいな強い精霊がそれらを統括している……っていうのがスタンダードなカタチなんだよ」
「ふぅん…………魚群の群れの長、みたいなものなワケかな。つまり」
今ひとつ理解しきってはいないものの、それでも理解できる分野で解釈をしようとしているのか。ポツリと呟くオルキヌスへとエールステゥは頷いてみせる。確かにそれは一番近い認識かもしれない、と。
「じゃあその長をどうにかすれば、群れはエルゥさんの言うことを聞くって事か」
「うん。その為にするのが契約、だね」
「…………それ大丈夫なの? 俺みたいな災難なことにならない?」
「大丈夫だよ。多分。一度こっちは打ち勝ってる訳だしね」
不安げに呟くオルキヌスの視線は黄金のランプに注がれている。そういえば、現在の彼とランプの魔神は契約者と契約された魔神……という関係になる訳で、心配するのも当然だろう。安心させる様に微笑んで見せるエールステゥだが、その足元、船底でカタカタと揺れている黄金のランプは不満げな声を漏らす。
『災難とは失礼な……早く汝が願いを決め我に願えば良いだけの事ではないか』
「いやぁ……そう言われても困るっていうか正直……契約解消を願えたりしない訳?」
『汝は我が契約を何だと思っているのだ』
「ぁー……ゴメン何でもない」
余計なことを聞いたとばかりに慌てた様子で操船に戻るオルキヌスと、そんな契約主相手にお小言を言い始めたランプの魔神を微笑ましげに眺めつつもエールステゥは船の往く先を見る。精霊との契約。それを果たしたとしてそんな事は始まりでしかない。
これから赴く先は炎の海。あの魔神が平気で海の中に居たのも、元よりあの海の出だからなのだろうか。何にせよ、一筋縄ではどうにもならない世界が待っていることだけは確実だ。テリメインの海の多様さに想いを馳せながら《門》に着くまでの間、少しだけ休むことに決めたエールステゥなのだった。
※ ※ ※ ※ ※
目的地に到着したのは正午前。
とりあえず二人を海上で待たせ、エールステゥは海へと飛び込んだ。
潜ること暫し、久しぶりに訪れた《アッシュフォードの門》には相変わらず精霊の姿がある。青い海の底でこうして燃え盛る炎を見る、というのは酷く珍しい経験で何度見ても違和感しか無い。こればっかりは仕方がないか、と苦笑するエールステゥが静かに泳ぎながらも近づけば向こうもまた気づいた様子で顔を上げた。
『……む、お前は』
「先日はどうも」
頭を下げれば、炎の巨霊イフリートは苦い顔で唸る。
『どうも、ではない。何だまだお前達は《レッドバロン》に行っていなかったのか』
せっかく自分が許し道を譲ったと言うのに、と言わんばかりのイフリートにエールステゥは苦笑を返す。
「行きたいのは山々なんだけど……私達の使う船は普通の海用で、それも漁師さんが使うような素朴なものだから。対策を取らないと燃えてしまいそうだもの」
『スキルストーンもあるのだ、泳げば良いでは無いか』
「ソレもそうなんだけど、海の中でずっといるのは元々陸地に暮らす生き物としては落ち着かないものだから。それに船を置いていけないし」
『ふぅむ……なかなか面倒な生き物だな、地上の生き物は』
「気にしない人も居るんだろうけど、ね。船も、仲間の元々使っていた大切な財産でもあるから……どうにか持っていきたいと思ってて」
『それで俺の所に赴いた、と』
鋭いイフリートの眼差しが、威嚇するように相手を見据える。
しかしそんな視線も気にした風はなく、エールステゥはただ穏やかに微笑んだままだ。
『……何が望みだ、人間』
「貴方の助力を」
『俺は此処を離れるつもりはない。お前の助力など、どうやってやれという』
「貴方の統べる精霊としての力を、私に貸して欲しいの」
『何だと……?』
マジマジとエールステゥを穴が空くほどに観察したイフリートは、何かに気付いたように舌打ちした。
『お前は……そうか、精霊術師か!』
「それが専門ではない、けどね」
瞳を伏せるエールステゥはその左の肩口に手を添える。蒼い海の底でぼんやりと輝きが灯った。植物か、或いは翼か……何かをモチーフにしたのであろう不可思議な紋様が浮かび上がったのは一瞬の事だ。普段は隠蔽している、それは精霊術師としての素質を認められた故に刻まれた特別な徴である。
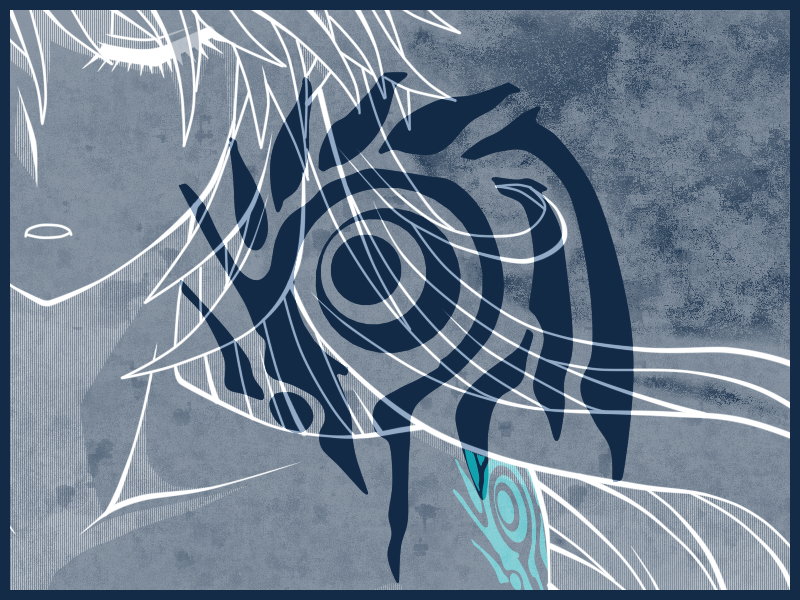
「才さえあるならば学べる技能ではあるから。……もっとも、適正やその他諸々もあるから誰もが進んで学ぶものでもないし、あまり精霊を扱えるっていうのは一般的とは言えないから表立って表明出来るものでもないんだけど」
実際、精霊の使い手というのは警戒される率も高いのは嘘ではない。適正こそ必要だが、賢者の塔と言った学術・研究機関、或いは使い手による指導によって純粋に技術を極めれば身につけられる一般的な術と異なり、どうしても第三者の存在……精霊が関わってくるからだ。精霊の中にはかつて土地神であったり異教の神だったものが零落した、といった存在も少なくはない。そういう関係もあって、秘するのが基本な技能でもあった。
とはいえ、冒険者等という危険と隣り合わせの生業をしていれば使える物は精霊どころか神でも使う、なんての話もザラである。エールステゥもまた冒険者生活の中で活用できると見てわざわざ出向き、学び、そうして精霊術師としての技術を身につけた一人であった。
「改めてお願いするよ、炎熱の導き手……炎の巨霊イフリート。貴方の助力が私は欲しいの」
『ふん、精霊術師か……奴らにも多種多様な分派が存在する。俺は場合によってはお前の敵にならねばならん……お前は一体、どの派の精霊術師だ』
警戒の色も濃いイフリートの様子を窺いながらもエールステゥは唸る。
「そう警戒しないで欲しいんだけどな……」
『そうもいかん。……無理矢理に場から精霊を引き剥がし、その力を使い潰し、精霊を苦しめる精霊術師も世の中には存在する。俺ぐらいにもなればその程度で消滅するほどではないが、かといって見過ごす訳にもいかんからな』
さあどうなんだ、と睨みつけてくるイフリートへと、ため息混じりにエールステゥは返した。
「私は、力を示し助力を約す……友誼の派閥。元より、貴方達精霊の領域を乱すつもりは無いし無理強いもしない。せめて、炎の海を安全に船が渡るための助力が欲しいだけ。……それでも駄目かな?」
『駄目だ。保険が欲しい』
「……ならば、期限を設けるのはどうかな?」
『期限、だと?』
訝しげなイフリートへと、エールステゥは頷いてみせる。
「そう。永続的な契約ではなく一時的なものってこと。私は元々この世界の人間じゃない。だから、貴方とずっと縁を結び続けることはきっと無理だと思うしね。……私がこの世界に存在する間だけ、貴方の助力を願います」
『ふぅむ……』
流れた沈黙は短かった。
暫し思案を巡らせていた様子のイフリートは渋々といった表情で口を開く。
『……良いだろう。お前と契約を結んでやる。ただし、期限はお前がこの世界を出るまでの間……とする。構わんな?』
「ええ、勿論。……ありがとう」
ホッとした表情でエールステゥが返せば、炎の精霊はそっぽを向いた。
『ふん……お前とお前の仲間は、俺を打ち倒した者だからな。その程度の譲歩はしてやらんではない』
ぶっきらぼうな口調ながら、そこに敵意はない。不器用な返答に思わず綻んだエールステゥの笑顔にイフリートが気付いて、さっさ契約を済ませた後逃げるように退散するのはもう少し後の話だった。
※ ※ ※ ※ ※
「……っぷは」
「あっ、エルゥさんお帰り!」
『首尾の方はどうだ』
水面から顔を出した途端に飛んできた声は二つ。それにクスクスと笑いながらもエールステゥは親指と人差し指で丸を作って見せた。
「バッチリだよ! 待たせてごめんね」
「構わないって。これで俺の船であの海域を渡れるってことだろ?」
「勿論! すぐに対策を施すね!!」
スイスイと波間をかきわけ船へと近付いた。波に洗われ、使い込まれた故の傷みや傷がアチコチに見える船底に手を触れる。
「魔神さん! 設計図!!」
『今、持っていく。少し待て』
黄金のランプから溢れ出た煙が人にも似た大きな腕を成す。その指先がつまむのは一枚の羊皮紙だ。そこにはびっしりと単純な図形を組み合わせ作り出された不可思議な紋様が描かれている。エールステゥとランプの魔神が共同で組んだ、船の保護のための術式だ。炎の精霊、その力の一端を紋様として転写することでそこを媒介に船全体に保護の術式を展開する、という代物である。何と、炎の海に浮かべている限り半永久的に機能するという優れ物になったのは、ランプの魔神が太古から知り得た知識を活用したからだ。
エールステゥはつい先程契約で得た炎の精霊の力を指先に集め、船の腹をなぞる様にして文様を注意深く転写していく。そうして作業すること数分と言った所か。パン、と手を叩いてエールステゥは満足げに笑みを浮かべた。
「これでよし、っと! 準備完了だよ、オルキ君!」
「リョーカイ! んじゃ、エルゥさんも乗った乗った!」
頷けば、エールステゥは船の上から差し出されるオルキヌスの手を取る。まだ年若いながらに逞しいその腕は、軽鎧を装備したままの女一人を軽々と引っ張り上げて見せた。太陽のように眩しくも不敵な笑みを浮かべ、オルキヌスは言う。
「お膳立ても出来たことだしさ。せっかくだし、《レッドバロン》の探索に行ってみない?」
今直ぐ新たな海に本格的に漕ぎ出してしまいたい、と言う表情の少年にエールステゥとランプの魔神は顔(と言っても魔神の方は顔なんて見えないのでランプを見るしか無いのだが)を見合わせる。
「オルキ君たら気が早いんだから」
『しかし気持ちは分からんではない。……行ってみても問題はなかろう』
「そうだね。……じゃあ、オルキ君。操船はよろしく頼むよ?」
後は任せた、とばかりに声をかければやる気満々で少年は櫂を手に宣言した。
「任せといてよ! ……それじゃ、一路《レッドバロン》へ!!」
水面を統べるように疾走りだす船に揺られつつ、ずぶ濡れの身を拭く中でエールステゥは空を見上げた。今日は本当に快晴だ。雲一つない。それが良いことなのか悪いことなのかは別としても、良い旅立ち日和である事は確かだった。探索と冒険の舞台は穏やかな海《セルリアン》から灼熱の海《レッドバロン》へと移り変わる事になるだろう。
次にこの海域に訪れるのは何時になるのだろうか。そんな事を思いながらも、エールステゥは瞳を伏せた。