16日目
世界は幾つもの層から出来ている。
いや、正確には幾つもの層と認識する者も居る……という方が正しい。
見え方は千差万別だ。
常に同じ物の見方をしている者がどれほどいるというのだろうか。
例えば、自分と相手が同じ〝赤色〟を見ていたとして、その赤が全く同じ赤だとは限らないように。
ある意味、人の数だけ世界は確かに存在し得るのかもしれない。
……人ですらそうならば、人ですら無いモノは?
目に映るソレがもし人と異なるとして、それは決してオカシイ話ではないのだ。
■ ■ ■ ■ ■
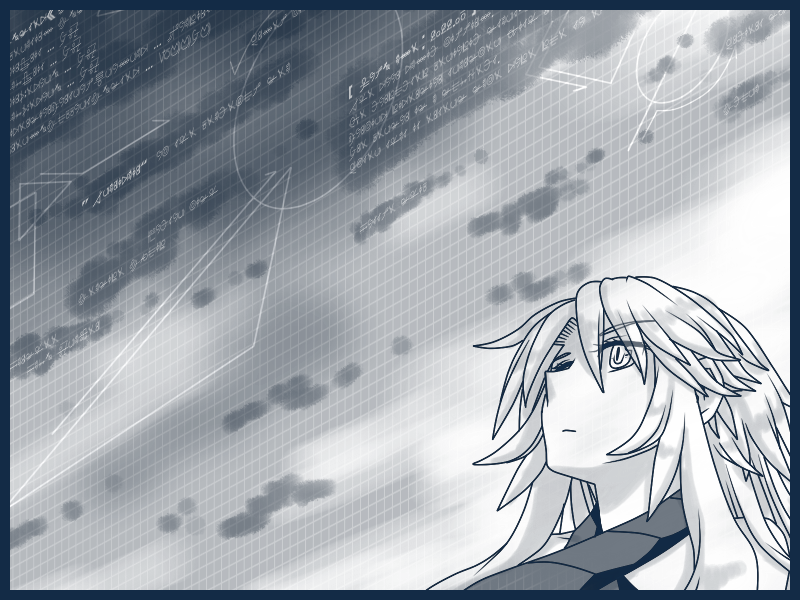
息を詰める。目を凝らす。来るぞ来るぞと覚悟を決めて受け止めた激しい波は確かに意識を強く揺すぶったが、今の所はそれだけだった。ただ気怠い疲労感だけが一瞬で通り過ぎた奔流の爪痕を確かに刻んでいる。とはいえ、その負荷の具合は想定したよりもまだ軽くて、その事に気が緩みそうになる。
(ダメ……)
一瞬振れそうになる視界。しかしそれを自らの意志で固定する。今は揺らぐ時ではなく、気を緩めるべきでもない。改めて大きく息を吸ってそして吐いた。落ち着いていく精神。研ぎ澄まされていく感覚。広がっていた眼前の《海》は確かに静けさを取り戻したようだった。
それはただの海ではない。触れることも出来なければ、見ることも普通ならば不可能だろう。この特殊な海域……灼熱の海《レッドバロン》や渦潮の海《ストームレイン》を始め全ての領域を含む〝テリメイン〟と呼称される場全てと層を別とする場所に広がる不可視の海だ。
とても広く、形を刻々と変えつつも流れていくソレを目視できる者はどれほどいるのかわからない。だが、少なくともたった独りきりではないという事をエールステゥは確信している。
「蒼のトゥク・トリ……彼は、少なくとも存在を確信している。見えているかは別としても、確かに言っていたもの」
ゆっくりと開いていた瞳を細めながら呟く。その左目は今は煌々と輝きを宿しているのが傍目にも判る程、異彩な気配を放っていた。縦に割れた瞳孔がキュッと縮まる。彼の言葉を思い出す。
「情報の流れ……って言ってたものね。彼は私が視えてるものがどういうカタチをしているのかを把握していたからだ、とは思うけれど」
ふぅ、とため息を付きながらエールステゥは眼前を見た。目の前には青い空の下、浅く広がる砂浜の一角に大きな黒曜石を組み合わせて造られたような枠がそびえ立っている。エールステゥをテリメインに引きずり込んだのだろう『門』の遺物だ。ここは、初めて異世界に来たと気付いた、あの浜辺だった。
今日は探索の合間の時間を割いて久々に此処に来たのだ。それは、遺跡の存在とその無事を確認するためだった。一応コレが元の世界に繋がる可能性が一番高い遺物である。うっかり自然災害などで失われては困るし、もしもその可能性があるならば対策を講ずるべきだろうか……と思ったからでもあった。
が、その心配は正直杞憂だったらしい。『門』は相変わらずそこに鎮座しているだけであり、『門』自体は勿論だが周囲も何一つ前に来た時と変化はないと言って良い。少しだけ砂浜のカタチや流れ着いている漂流物(大体が貝殻やら何やらといった物ばかりだ)の分布が変わっている程度で至って平穏な様子である。
それもまあ当然か、とエールステゥは苦い笑みを深めた。何と言っても此処は平穏な海《セルリアン》の一角でもある。確かにたまに物騒な生物こそ徘徊しているようではあるが、それも新海域方面に大分進んだ先での話であり海底探索協会の庇護化にあるこの近辺では野生生物以外の姿は滅多にない。
仮になにかあるとして、それは探索者なり海賊なりが狼藉を働く場合ぐらいではないのだろうか。まあ、どう贔屓目に見てもこんなただの石の枠に、興味があればの話だが。
その《門》の前に立つエールステゥは左の瞳で周囲を見回す。
青い空と青い海、そしてその中に立つ黒い『門』。その全てに薄っすらと紗がかかっている様な、そんな光景が視界には広がっている。まるで景色そのものが絵画になってしまった、そんな現実との乖離感……とでも言えば良いのだろうか。現実味が遠ざかる中に、まるで静かに打ち寄せては遠ざかる波の様に淡く煌めく無数の文字とも図形とつかない何かが蠢いている。
目を凝らしてもそれは解読も出来ない謎の記号でしか無い。その筈だ。様々な古代言語を仕事柄身につけているエールステゥの知識のうちには、少なくとも存在しない何かなのは確かだった。
それだというのに何故だろうか。意識を集中させればそこに蠢く記号らしき何かが何を示しているのかが判るのだ。まるで前々から知っていたことを改めて思い出して行くような、頭の奥底から中身が引きずり出されるようなそんな気持ちの悪い感覚と共に。
「……ッ、やっぱりこの眼……便利だけど負荷が大きすぎる……ッ」
普段はその力を発揮しないようにと暗示をかけているが今は少しだけそれを解いている。だというのに、コレほど気持ちが悪いとは。慣れがないだけなのか、それとも副作用なのか。不快感に眉根をしかめつつも瞳を通して流れ込んでくるその情報を何とか意識して選別し、必要なものだけを拾い上げようと試みる。
左目が覚醒した謎のこの力を利用して、『門』についての情報を得られるのではないか。そんな事を思い付いたのはつい数日前の事だ。少しずつ暗示のかけ具合を自在に調整出来る様になったという事や、探索行も程度安定期に入ってきたというのがもう一つの理由でもある。一度訪れた先も、再度訪れた時に何か気づくことが出て来るかもしれない……という一縷の望みもあった訳だが。
「現状、新しい情報を見付けるとか以前の問題だよね……コレ」
情報がない、どころではない。逆である。感じ取れる情報量が多すぎるのだ。何が必要で何が不要なのか、判別したくとも膨大な量が流れ込んでくるものだから、それを絞るのに四苦八苦しているのである。
かと言って絞りすぎればあまりにも抽象的で何が何やら分からない。例えるならばひとつひとつの単語を呼んだだけで古典文学の中身が判るかどうか、と聞かれている様な……そんなダメダメな状態なのである。
別にコレはエールステゥの制御が甘いだとか未熟だとかそういう問題だけではないのだが。どうやら、この『門』その物が内包する情報があまりに多すぎるのである。
ほんの触りだけ感じ取った気配では、機能面は勿論だが製造法やらその材質の詳細は勿論のこと、内包する技術に関する膨大な数の法則や公式郡にこの《門》の経てきた経験情報エトセトラエトセトラ……挙げ始めたらキリがない。
エールステゥは「ううう……」と唸りつつも疲れてきた目を一旦閉じる。瞼の裏に瞳が隠れてしまえば、まるでグズグズと延々と弄られ続けていた様な頭の奥の違和感は消え失せた。本当に、視覚を介してしか影響は現れないのだ。かといってずっと目を閉じているわけにも行かないのだが。
とりあえずはと暗示をかけ直せばやっと両目を開いた。ぼやけていた左目の視界がやっと戻ってくれば、大分見慣れてきた《セルリアン》のキレイな碧天が目にしみた。
「発想は悪くなかったんだけどなぁ……思ったよりもコレは、難易度が高すぎる気がする」
砂浜に座り込んで、腰に下げていたカバンから水筒を取り出した。蓋を開けて一口。中身はタダの清水だが、それでも潮風に吹かれ海を泳いだ後でサンサンと降り注ぐ日光の下に居た身には極上の酒と同じぐらいに美味に感じられてはふぅと思わず息をつく。
「もう少しこっちに情報の整理整頓するための知識が必要なのと、眼の力の制御をどうにかしないと厳しい感じがする……何度やっても、多分疲れるだけだよね。今は」
無駄に体力を削るだけだ、と見切りをつけたのだ。
実際の所、結構な時間をかけて既に色々自分なりに調整しようと試みては見たのだがどうもうまく行かなかったのである。もう少し粘っても構わないといえば構わないが、あまり遅くなると合流予定の仲間が心配するのもある。このあたりが潮時だろう。
恨めしげに『門』を一度睨めばエールステゥは踵を返した。砂浜の端には、此処まで来るのに使った小さな小舟がある。前に世話になったあの漁師から借りたものである。毎度唐突に頼っているわけだが、それでも手助けを惜しまずに居てくれるのだからありがたいものだ。
「世界を多層化して見せる瞳……ね。出処は謎だけど、コレのこともそのうち調べないと……かな」
こうして暮らしている世界の上に上からかぶさるように広がる薄暗い蒼の世界。
左目から視えた浅く冷たい海の底に居るような、そんな気配を感じる景色を思い出して険しい表情を浮かべるエールステゥ。波の音も潮の香りもしなかったが、あれは確かに《海》だった。ただしそこに満ちているのも泳いでいるのも不可思議な記号の塊たちだけで、生き物の気配は欠片も見当たらなかったけれど。
言うなれば、アレは《情報の海》とでも言えば良いものなのだろうか?
元の世界に戻るための手段探し。当初の謎はそれだけだった。だが、今は違う。エールステゥを悩ませる新たな謎をこの世界で解き明かそうとするならば、きっと自分だけではどうにもならないのだろう。
「ヴィーズィー……貴女はどこまで知っていて、私に何をさせようとしているの……?」
海竜の手助けにとエールステゥを差し向けたのは、この眼の力を確信していたからだろうと蒼のトゥク・トリは言っていた。ならば、ヴィーズィーは全てを知っているのだろうか。去り際の海竜は敢えて何も言わず立ち去ったが。
「……何とかして、また捕まえないとね」
ポツリと呟いた声には、どこまでも本気なのだろうエールステゥの気迫が滲み出ていたせいか。いつもより低く、そして重々しかった。